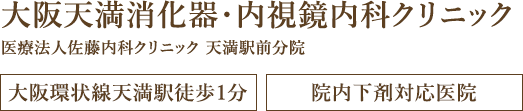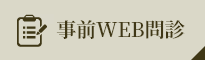下痢
 下痢は水分量の多い便で、やわらかく形が保てないものから水っぽいものまで様々です。排便時に腹痛をともなうことが多く、排便回数も増加します。吸収できる水分が減るため脱水リスクが高く、特に子どもや高齢者は注意が必要です。脱水症状が現れたらすぐに医療機関を受診しましょう。市販の経口補水液や薄い食塩水にブドウ糖を入れたもので水分補給するのも有効ですが、必ず常温や湯冷まし程度の温度のものを飲むようにしてください。冷えている飲み物は刺激が強く、下痢を悪化させる可能性があります。なお、嘔吐をともなう場合、急激な脱水が進む可能性がありますので、できるだけ早く医療機関を受診してください。
下痢は水分量の多い便で、やわらかく形が保てないものから水っぽいものまで様々です。排便時に腹痛をともなうことが多く、排便回数も増加します。吸収できる水分が減るため脱水リスクが高く、特に子どもや高齢者は注意が必要です。脱水症状が現れたらすぐに医療機関を受診しましょう。市販の経口補水液や薄い食塩水にブドウ糖を入れたもので水分補給するのも有効ですが、必ず常温や湯冷まし程度の温度のものを飲むようにしてください。冷えている飲み物は刺激が強く、下痢を悪化させる可能性があります。なお、嘔吐をともなう場合、急激な脱水が進む可能性がありますので、できるだけ早く医療機関を受診してください。
下痢の原因
 下痢の原因として多いのが、ウイルスや細菌などの感染から起こる感染性胃腸炎です。この場合、自己判断で下痢止めの市販薬を服用すると毒素が長時間腸内に留まることになってとても危険です。他に、クローン病や潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群、そして大腸がんなどでも下痢の症状を現すことがあります。数日で症状が解消する場合には感染症の可能性がありますが、重い症状がある場合や何度も下痢を繰り返すようでしたら、大腸疾患の可能性がありますので、消化器科を受診しましょう。
下痢の原因として多いのが、ウイルスや細菌などの感染から起こる感染性胃腸炎です。この場合、自己判断で下痢止めの市販薬を服用すると毒素が長時間腸内に留まることになってとても危険です。他に、クローン病や潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群、そして大腸がんなどでも下痢の症状を現すことがあります。数日で症状が解消する場合には感染症の可能性がありますが、重い症状がある場合や何度も下痢を繰り返すようでしたら、大腸疾患の可能性がありますので、消化器科を受診しましょう。
下痢から考えられる疾患
感染性胃腸炎
原因となる病原体はウイルスと細菌に大きく分けられ、治療法が異なります。激しい下痢と嘔吐が主な症状で、脱水を起こしやすいので注意が必要です。十分な水分補給が必要ですが、飲んでも嘔吐してしまう場合にはすぐに受診してください。また、感染性胃腸炎の場合には下痢止めや吐き気止めの服用が重篤な症状につながることが多いため、できるだけ早く受診するようにしましょう。
細菌性胃腸炎の場合には抗菌剤による治療が有効ですが、ウイルスによる胃腸炎の場合は水分補給と安静を保ちます。脱水の危険性がある場合には、点滴などが必要です。
なお、便や嘔吐物の処置や廃棄では十分な注意が必要です。感染を広げないために手袋、マスク、エプロンを着用して処理し、石鹸でしっかり手を洗いましょう。
潰瘍性大腸炎
下痢や腹痛が続き、血便や微熱などが起こることもあります。こうした症状がいちど治まってもしばらくすると再び現れ、それを繰り返します。活動期(再燃期)と寛解期を繰り返す大腸の慢性的な炎症疾患で、原因はまだはっきりとわかっていません。炎症を解消させて良い状態を保つ治療はできますが、根本的な治療法はなく、難病指定されています。
クローン病
下痢や血便、腹痛といった症状が現れ、治っては再発するを繰り返します。発症の原因がわからず難病指定されている潰瘍性大腸炎と似ていますが、クローン病の病変は口から肛門まで消化管の全域に炎症が生じる可能性があります。潰瘍性大腸炎よりも広範囲に渡って炎症を起こすことがあります。また、特定の食品に炎症リスクがある場合もあり、食事の制限が必要になることもあります。
大腸がん
大腸がんは、自覚症状に乏しいですが、ある程度進行すると血便、便秘・下痢を繰り返すといった症状が現れることがあります。大腸がんのサイズが大きくなると腸の内径が狭くなって便の通過が妨げられ、擦れて出血して血便が起こることがあります。大腸がんによって腸が狭窄するとそこに便がたまって便秘になり、それを排出させるために水分が多く分泌されて下痢になるというケースもあります。大腸がんがさらに大きくなると便が通過できず、腸閉塞を起こすこともあります。この場合には緊急手術が必要になります。
早期の大腸がんや、将来がん化する可能性がある大腸ポリープは、内視鏡検査で発見が可能です。
過敏性腸症候群
下痢や便秘、腹痛、膨満感などの症状が現れます。大腸粘膜に炎症などの病変がなく、蠕動運動などの機能的な問題によって起こっていると考えられています。典型的な症状として、緊張などをきっかけに強い腹痛が突然起こり、水のような激しい下痢になって、排便後は腹痛が治まります。